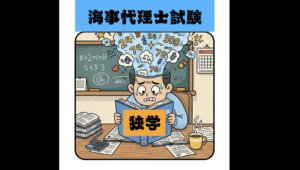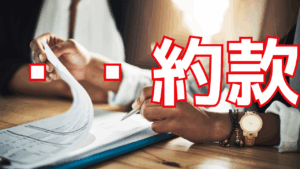目次
短答式問題
指示: 各問題について、2~3文で簡潔に解答してください。
- 港湾運送事業法の目的は何ですか?
- 港湾運送事業法における「港湾運送事業」の7つの種類を挙げてください。
- 国土交通大臣が港湾運送事業の許可を与える際に審査する5つの許可基準とは何ですか?
- 内航海運業法に基づき、総トン数百トン以上または長さ三十メートル以上の船舶で内航海運業を営もうとする者が行うべき手続きは何ですか?
- 造船法において、国土交通大臣の許可が必要となる施設の「新設等」にはどのような行為が含まれますか?また、その対象となる船舶の規模はどのようになっていますか?
- 海上運送法における「一般旅客定期航路事業者」が運送約款を定めたり変更したりする際に必要な手続きは何ですか?
- 船員法が定める、船員の船舶所有者に対する債権の消滅時効について説明してください。
- 海上交通安全法における「巨大船」の定義と、巨大船が航路を航行しようとするときに船長が取るべき措置を説明してください。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律において、船舶から油を排出することが例外的に許可されるのはどのような場合ですか?
- 商法における船舶所有権の移転が第三者に対抗するための要件は何ですか?また、総トン数二十トン未満の船舶には、この要件に関する規定は適用されますか?
——————————————————————————–
解答
- 港湾運送事業法(第一条)の目的は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図ることです。これにより、最終的に公共の福祉を増進することを目指しています。
- 港湾運送事業法(第三条)で定められている事業の種類は、一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業、検数事業、鑑定事業、検量事業の7つです。
- 港湾運送事業法(第六条)に基づく許可基準は、①適切な施設と労働者を有すること(一般港湾運送事業等の場合)、②事業遂行上適切な計画を有すること、③責任範囲が明確な経営形態であること、④確実な経理的基礎を有すること、そして⑤検数事業等については公正かつ適正な実施体制が整備されていることです。
- 内航海運業法(第三条)に基づき、総トン数百トン以上または長さ三十メートル以上の船舶で内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
- 造船法(第二条)において許可が必要な行為は、施設の「新設、譲り受け、若しくは借り受け」です。対象となるのは、総トン数五百トン以上または長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造または修繕ができる施設です。
- 海上運送法(第九条)によると、一般旅客定期航路事業者は運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。この約款を変更しようとするときも同様に認可が必要です。
- 船員法(第百十七条)では、船員の船舶所有者に対する債権は、原則として2年間行使しないと時効により消滅します。ただし、給料その他の報酬の債権については、その期間が5年間と定められています。
- 海上交通安全法(第二条)において、「巨大船」は長さ二百メートル以上の船舶と定義されています。巨大船が航路を航行しようとするとき、船長はあらかじめ、船舶の名称、航行予定時刻、連絡手段などを海上保安庁長官に通報しなければなりません(第二十二条)。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(第四条)によると、①船舶の安全確保や人命救助のため、②船舶の損傷などやむを得ない原因による場合で、継続的な排出防止措置をとったとき、③政令で定める基準に適合する場合、④海上保安庁長官の承認を受けた試験研究のため、といった場合に例外的に油の排出が許可されます。
- 商法(第六百八十七条)では、船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ船舶国籍証書に記載しなければ第三者に対抗することができません。ただし、この規定は総トン数二十トン未満の船舶には適用されません(第六百八十六条)。
——————————————————————————–
論述式問題
指示: 以下のテーマについて、提供された資料全体から関連情報を統合し、論述形式で解答を構成する準備をしてください(解答の作成は不要です)。
- 「港湾運送事業法」「内航海運業法」「海上運送法」「造船法」の4つの法律における、事業の開始、変更、休廃止に関する手続き(許可、認可、登録、届出)の違いを比較し、それぞれの規制の目的と性格について論じなさい。
- 国土交通大臣は、海事関連法規において広範な権限を持っています。提供された資料に基づき、国土交通大臣が持つ「許可」「認可」「命令(改善、停止、変更等)」「届出の受理」といった権限の具体例を複数挙げ、それらが各法律の目的達成にどのように寄与しているかを説明しなさい。
- 「海上交通安全法」と「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」は、それぞれ異なる側面から海上における安全と環境保全を目指しています。両法が定める船舶の航行・運航に関する具体的な規制(航法、通報義務、設備設置義務など)を比較し、その目的と実効性について論じなさい。
- 提供された資料には、複数の法律で「交通政策審議会」または「運輸審議会」への諮問や意見聴取が義務付けられています。これらの審議会が関与する事案(例:事業許可の取消し、安全管理規程の方針策定、技術に関する勧告など)を具体的に挙げ、海事行政におけるこれらの審議会の役割と重要性について考察しなさい。
- 「船員法」「商法」「船舶職員及び小型船舶操縦者法」は、船長や船員の権利、義務、責任について多角的に規定しています。船長の代理権、災害補償、職務上の責任、解任に関する規定などを横断的に整理し、海上における人的要素の重要性とそれを支える法的枠組みについて論じなさい。
——————————————————————————–
用語集
| 用語 | 定義 | 出典 |
| 一般港湾運送事業 | 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における受取・引渡と、それに先行・後続する荷役、運送、保管等の行為を一貫して行う事業。 | 港湾運送事業法 第二条・第三条 |
| 海上運送状 | 運送人または船長が、荷送人または傭船者の請求により、運送品の船積み後または受取後に交付する、船積みまたは受取があった旨を記載した書類。 | 商法 第七百七十条 |
| 海上交通安全法が適用される海域 | 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海のうち、港則法に基づく港の区域や漁港の区域などを除いた、船舶交通がふくそうする海域。 | 海上交通安全法 第一条 |
| 海洋汚染等 | 海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊をいう。 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三条 |
| 海洋施設 | 海域に設けられる工作物で、政令で定めるもの。陸地との間に固定施設で往来できるものや、陸地から油等を排出するために接続して設けられるものを除く。 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三条 |
| 巨大船 | 長さ二百メートル以上の船舶。 | 海上交通安全法 第二条 |
| 共同海損 | 船舶及び積荷等に対する共同の危険を避けるために、船舶または積荷等について意図的に行われた処分によって生じた損害及び費用。 | 商法 第八百八条 |
| 港湾運送 | 他人の需要に応じて行う、港湾における貨物の積卸、運送、保管、検数、鑑定、検量などの行為。 | 港湾運送事業法 第二条 |
| 港湾運送関連事業 | 他人の需要に応じて、港湾において船舶の貨物の位置固定、荷造り、船倉清掃、船積貨物の警備などを行う事業。 | 港湾運送事業法 第二条 |
| 国際総トン数 | 千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づき、主として国際航海に従事する船舶の大きさを表す指標。閉囲場所の合計容積を基に算定される。 | 船舶のトン数の測度に関する法律 第四条 |
| 載貨重量トン数 | 船舶の航行の安全を確保できる限度内における貨物等の最大積載量を表す指標。 | 船舶のトン数の測度に関する法律 第七条 |
| 指定海域 | 地形及び船舶交通の状況からみて、非常災害発生時に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域として政令で定めるもの。 | 海上交通安全法 第二条 |
| 船舶 | 商行為をする目的で航海の用に供する船舶(ろかいのみで運転する舟などを除く)。 | 商法 第六百八十四条 |
| 船舶管理人 | 船舶共有者によって選任され、船舶共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する者。 | 商法 第六百九十七条、第六百九十八条 |
| 船荷証券 | 運送人または船長が、荷送人または傭船者の請求により、運送品の船積み後または受取後に交付する有価証券。運送品に関する処分はこの証券によって行われる。 | 商法 第七百五十七条、第七百六十一条 |
| 総トン数 | 日本における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標。国際総トン数の算定方法に準じ、国土交通省令で定める係数を乗じて算出される。 | 船舶のトン数の測度に関する法律 第五条 |
| 定期傭船契約 | 当事者の一方が、艤装した船舶に船員を乗り組ませ、一定期間相手方の利用に供することを約し、相手方がその対価として傭船料を支払うことを約する契約。 | 商法 第七百四条 |
| 内航海運業 | 総トン数百トン以上または長さ三十メートル以上の船舶による内航運送業(登録制)、およびそれ未満の船舶による内航運送業(届出制)を指す。 | 内航海運業法 第三条 |
| 廃油 | 船舶内において生じた不要な油。 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三条 |
| 廃油処理事業 | 一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業。 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三条 |
| 油 | 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の油及びこれらを含む油性混合物。 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三条 |
| 油濁防止管理者 | 船長を補佐し、船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務を管理するために、船舶所有者によって選任される船舶職員。 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第六条 |
| 油濁防止規程 | 油の不適正な排出の防止に関する業務管理や作業員の遵守事項などを定めた規程で、船舶所有者が作成し、船内に備え置くもの。 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第七条 |
| 旅客定期航路事業 | 旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)を使用して、定められた航路で定期的に旅客を運送する事業。 | 海上運送法 第二条・第三条 |
※ notebooklmで作成しています。
事実関係は、法令を再度確認して下さい。
誤記がありましたらお知らせ下さい。