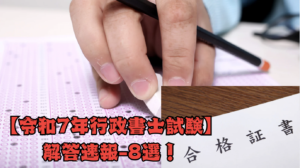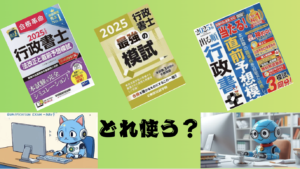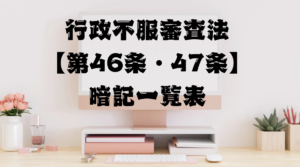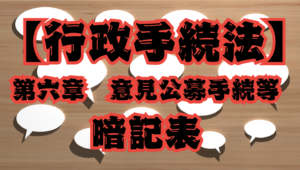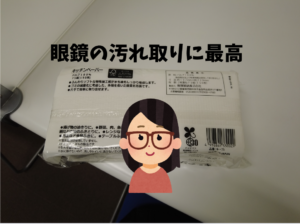令和 6 年度
行政書士試験問題
問題 2 訴訟の手続の原則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1 民事訴訟手続において、裁判長は、口頭弁論の期日または期日外に、訴訟関係を
明確にするため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、
または立証を促すことができる。
2 刑事訴訟手続において、検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重お
よび情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しな
いことができる。
3 非訟事件手続において、裁判所は、利害関係者の申出により非公開が相当と認め
る場合を除き、その手続を公開しなければならない。
4 民事訴訟手続において、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨およ
び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と
認めるべきか否かを判断する。
5 刑事訴訟手続において、検察官は、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜ
しめる虞のある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用してはならない。
2
問題 3 人格権と夫婦同氏制に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照ら
し、妥当でないものはどれか。
1 氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであ
るが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その
個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する。
2 氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部として、法律がその具体的な内容を規
律しているものであるから、氏に関する人格権の内容も、憲法の趣旨を踏まえつつ
定められる法制度をまって、初めて具体的に捉えられる。
3 家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であるから、氏をその個人の属する集団
を想起させるものとして一つに定めることにも合理性があり、また氏が身分関係の
変動に伴って改められることがあり得ることは、その性質上予定されている。
4 現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると、婚姻の際に「氏の変更を強制
されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえな
い。
5 婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲
法上保障される人格権の一内容とはいえず、当該利益を婚姻及び家族に関する法制
度の在り方を検討する際に考慮するか否かは、専ら立法裁量の問題である。
3
問題 4 インターネット上の検索サービスにおいて、ある人物Xの名前で検索をすると、
Xの過去の逮捕歴に関する記事等が表示される。Xは、この検索事業者に対して、
検索結果である URL 等の情報の削除を求める訴えを提起した。これに関する次の
記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。
1 個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対
象となるというべきであり、過去の逮捕歴もこれに含まれる。
2 検索結果として提供される情報は、プログラムによって自動的に収集・整理・提
供されるものにすぎず、検索結果の提供は、検索事業者自身による表現行為とはい
えない。
3 検索事業者による検索結果の提供は、公衆の情報発信や情報の入手を支援するも
のとして、インターネット上の情報流通の基盤としての役割を果たしている。
4 当該事実を公表されない法的利益と、当該情報を検索結果として提供する理由に
関する諸事情を比較衡量した結果、前者が優越することが明らかな場合には、検索
事業者に対して URL 等の情報を当該検索結果から削除することを求めることがで
きる。
5 過去の逮捕歴がプライバシーに含まれるとしても、児童買春のように、児童への
性的搾取・虐待として強い社会的非難の対象とされ、罰則で禁止されている行為
は、一定の期間の経過後も公共の利害に関する事柄でありうる。
4
問題 5 教育に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはど
れか。
1 義務教育は無償とするとの憲法の規定は、授業料不徴収を意味しており、それ以
外に、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用を無償としなければならない
ことまでも定めたものと解することはできない。
2 教科書は執筆者の学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、また、教科
書検定は検定基準に違反する場合に教科書の形態での研究結果の発表を制限するに
すぎないので、教科書検定は学問の自由を保障した憲法の規定には違反しない。
3 公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであ
るから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の
授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する。
4 国民の教育を受ける権利を定める憲法規定の背後には、みずから学習することの
できない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一
般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。
5 普通教育では、児童生徒に十分な批判能力がなく、また、全国的に一定の教育水
準を確保すべき強い要請があること等からすれば、教師に完全な教授の自由を認め
ることはとうてい許されない。
5
問題 6 選挙制度の形成に関する国会の裁量についての次の記述のうち、最高裁判所の判
例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
1 都道府県が歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実体を有する単
位である以上、参議院の選挙区選出議員に都道府県代表的な意義を付与し、その枠
内で投票価値の平等の実現を図ることは、憲法上許容される。
2 小選挙区制は、死票を多く生む可能性があることは否定し難いが、死票はいかな
る制度でも生ずるものであり、結局のところ選挙を通じて国民の総意を議席に反映
させる一つの合理的方法ということができる。
3 同時に行われる二つの選挙に同一の候補者が重複して立候補することを認めるか
否かは、国会が裁量により決定することができる事項であり、衆議院議員選挙で小
選挙区選挙と比例代表選挙との重複立候補を認める制度は憲法に違反しない。
4 政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用す
ることは国会の裁量に属し、名簿登載者個人には投票したいがその属する政党には
投票したくないという意思を認めない非拘束名簿式比例代表制もまた同様である。
5 参議院の比例代表選出議員について、政党が優先的に当選者となるべき候補者を
定めることができる特定枠制度は、選挙人の総意によって当選人が決定される点
で、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異ならず、憲法に違反しな
い。
6
問題 7 国会議員の地位・特権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 両議院の議員には国庫から相当額の歳費を受ける権利が保障されており、議員全
員を対象とした一律の措置としてであっても、議員の任期の途中に歳費の減額を行
うことはできない。
2 両議院の議員は、国会の会期中は、法律の定める場合を除いては逮捕されること
がなく、また所属する議院の同意がなければ訴追されない。
3 両議院の議員には、議院で行った演説、討論、表決について免責特権が認められ
ているが、議場外の行為については、議員の職務として行ったものであっても、免
責の対象とならない。
4 参議院の緊急集会は、衆議院の解散中に開催されるものであるが、その際にも、
議員に不逮捕特権や免責特権の保障が及ぶ。
5 議院が所属議員に科した懲罰には、議院自律権の趣旨から司法審査は及ばないの
が原則であるが、除名に関しては、手続の適正さについて審査が及ぶとするのが最
高裁判所の判例である。
問題 8 行政行為(処分)に関する次の記述のうち、法令の定めまたは最高裁判所の判例
に照らし、妥当なものはどれか。
1 処分に瑕疵があることを理由とする処分の取消しは、行政事件訴訟法上の取消訴
訟における判決のほか、行政不服審査法上の不服申立てにおける裁決または決定に
よってのみすることができる。
2 金銭納付義務を課す処分の違法を理由として国家賠償請求をするためには、事前
に当該処分が取り消されていなければならない。
3 処分取消訴訟の出訴期間が経過した後に当該処分の無効を争うための訴訟として
は、行政事件訴訟法が法定する無効確認の訴えのみが許されている。
4 処分Aの違法がこれに後続する処分Bに承継されることが認められる場合であっ
ても、処分Aの取消訴訟の出訴期間が経過している場合には、処分Bの取消訴訟に
おいて処分Aの違法を主張することは許されない。
5 瑕疵が重大であるとされた処分は、当該瑕疵の存在が明白なものであるとまでは
認められなくても、無効とされる場合がある。
7
問題 9 行政立法に関する次の記述のうち、法令の定めまたは最高裁判所の判例に照ら
し、妥当なものはどれか。
1 行政手続法が定める意見公募手続の対象となるのは、法規命令のみであり、行政
規則はその対象とはされていない。
2 法律の規定を実施するために政令を定めるのは内閣の事務であるが、その法律に
よる委任がある場合には、政令に罰則を設けることもできる。
3 法律による委任の範囲を逸脱して定められた委任命令は違法となるが、権限を有
する機関が取り消すまでは有効なものとして取り扱われる。
4 通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なか
かわりをもつようなものである場合には、当該通達に対して取消訴訟を提起するこ
とができる。
5 行政手続法が適用される不利益処分の処分基準において、過去に処分を受けたこ
とを理由として後行の処分に係る量定が加重される旨の定めがある場合には、当該
処分基準の定めに反する後行の処分は当然に無効となる。
8
問題10 行政法における一般原則に関する最高裁判所の判例について説明する次の記述の
うち、妥当なものはどれか。
1 特定の事業者の個室付浴場営業を阻止する目的で町が行った児童福祉法に基づく
児童福祉施設の認可申請に対し、県知事が行った認可処分は、仮にそれが営業の阻
止を主たる目的としてなされたものであったとしても、当該処分の根拠法令たる児
童福祉法所定の要件を満たすものであれば、当該認可処分を違法ということはでき
ないから、当該個室付浴場営業は当然に違法となる。
2 特定の事業者の廃棄物処理施設設置計画を知った上で定められた町の水道水源保
護条例に基づき、当該事業者に対して規制対象事業場を認定する処分を行うに際し
ては、町は、事業者の立場を踏まえて十分な協議を尽くす等、その地位を不当に害
することのないよう配慮すべきであるが、このような配慮要請は明文上の義務では
ない以上、認定処分の違法の理由とはならない。
3 法の一般原則である信義則の法理は、行政法関係においても一般に適用されるも
のであるとはいえ、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、
租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用により当該課税処分を違
法なものとして取り消すことは、争われた事案の個別の状況や特段の事情の有無に
かかわらず、租税法律主義に反するものとして認められない。
4 地方公共団体が将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、当該施策が
社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることは当然であるが、当該地方公
共団体の勧告ないし勧誘に動機付けられて施策の継続を前提とした活動に入った者
が社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合において、地方
公共団体が当該損害を補償するなどの措置を講ずることなく施策を変更すること
は、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信
頼関係を不当に破壊するものとして違法となる。
5 国の通達に基づいて、地方公共団体が被爆者援護法*等に基づく健康管理手当の
支給を打ち切った後、当該通達が法律の解釈を誤ったものであるとして廃止された
場合であっても、行政機関は通達に従い法律を執行する義務があることからすれ
ば、廃止前の通達に基づいて打ち切られていた手当の支払いを求める訴訟におい
て、地方公共団体が消滅時効を主張することは信義則に反しない。
(注) * 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
9
問題11 会社Xは、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)に基づく免許を受け
て不動産取引業を営んでいる。ところが、Xの代表取締役であるAが交通事故を起
こして、歩行者に重傷を負わせてしまった。その後、自動車運転過失傷害の罪でA
は逮捕され、刑事裁判の結果、懲役 1 年、執行猶予 4 年の刑を受けて、判決は確定
した。宅建業法の定めによれば、法人の役員が「禁錮以上の刑」に処せられた場
合、その法人の免許は取り消されるものとされていることから、知事YはXの免許
を取り消した(以下「本件処分」という。)。
この事例への行政手続法の適用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 本件処分は、許認可等の効力を失わせる処分であるが、当該許認可等の基礎と
なった事実が消滅した旨の届出に対する応答としてなされるものであるから、行政
手続法のいう「不利益処分」には当たらない。
2 本件処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官または司法警
察職員がする処分を契機とするものであるので、行政手続法の規定は適用されな
い。
3 本件処分は、その根拠となる規定が法律に置かれているが、地方公共団体の機関
がする処分であることから、行政手続法の規定は適用されない。
4 本件処分は、申請に対する処分を取り消すものであるので、本件処分をするに際
して、行政庁は許認可等の性質に照らしてできる限り具体的な審査基準を定めなけ
ればならない。
5 本件処分は、法令上必要とされる資格が失われるに至ったことが判明した場合に
必ずすることとされている処分であり、その喪失の事実が客観的な資料により直接
証明されるものであるので、行政庁は聴聞の手続をとる必要はない。
(参考条文)
宅地建物取引業法
(免許の基準)
第 5 条① 国土交通大臣又は都道府県知事は、第 3 条第 1 項の免許を受けようと
する者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付
書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が
欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一~四 略
五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなった日から 5 年を経過しない者
六 以下略
② 以下略
10
(免許の取消し)
第 66 条① 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引
業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さな
ければならない。
一 第 5 条第 1 項第 1 号、第 5 号から第 7 号まで、第 10 号又は第 14 号のいず
れかに該当するに至ったとき。
二 略
三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第 5
条第 1 項第 1 号から第 7 号まで又は第 10 号のいずれかに該当する者がある
に至ったとき。
四 以下略
② 以下略
問題12 行政指導についての行政手続法の規定に関する次のア~エの記述のうち、妥当な
ものの組合せはどれか。
ア 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権
限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠
となる法令の条項等、行政手続法が定める事項を示さなければならない。
イ 地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律で定
められている場合に限り、行政指導に関する行政手続法の規定が適用される。
ウ 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置
かれているものを受けた相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合
しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中
止その他必要な措置をとることを求めることができる。
エ 意見公募手続の対象である命令等には、審査基準や処分基準など、処分をするか
どうかを判断するための基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ
11
問題13 審査基準と処分基準に関する次の記述のうち、行政手続法に照らし、妥当なもの
はどれか。
1 審査基準を公にすることによって行政上特別の支障が生じる場合、行政庁が当該
審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
2 処分基準は、不利益処分を行うに際して、その名あて人からの求めに応じ、当該
名あて人に対してこれを示せば足りるものとされている。
3 行政庁が審査基準を作成し、それを公にすることは努力義務に過ぎないことか
ら、行政庁が審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
4 審査基準を公にする方法としては、法令により申請の提出先とされている機関の
事務所において備え付けることのみが認められており、その他の方法は許容されて
いない。
5 行政庁が処分基準を定めることは努力義務に過ぎないが、処分基準を定めた場合
には、これを公にする法的義務を負う。
問題14 行政不服審査法における審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれ
か。
1 審査請求は、審査請求人本人がこれをしなければならず、代理人によってするこ
とはできない。
2 審査請求人以外の利害関係人は、審査請求に参加することは許されないが、書面
によって意見の提出をすることができる。
3 多数人が共同して審査請求をしようとする場合、 1 人の総代を選ばなければなら
ない。
4 審査請求人本人が死亡した場合、当該審査請求人の地位は消滅することから、当
該審査請求の目的である処分に係る権利が承継されるか否かにかかわらず、当該審
査請求は当然に終了する。
5 法人でない社団または財団であっても、代表者または管理人の定めがあるもの
は、当該社団または財団の名で審査請求をすることができる。
12
問題15 行政不服審査法(以下「行審法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なも
のはどれか。
1 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、または金銭の給付
決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分については、行審法の規定
は適用されない。
2 行審法が審査請求の対象とする「行政庁の不作為」には、法令に違反する事実が
ある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていない場合も含まれ
る。
3 地方公共団体の機関がする処分でその根拠となる規定が条例または規則に置かれ
ているものについては、行審法の規定は適用されない。
4 地方公共団体またはその機関に対する処分で、当該団体または機関がその固有の
資格において処分の相手方となるものについては、行審法の規定は適用されない。
5 行審法は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める審査
請求で、自己の法律上の利益にかかわらない資格でするものについても規定してい
る。
13
問題16 行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」
という。)との違いに関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれ
か。
ア 行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただ
し、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書」と
いう。)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期
間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書は置いていない。
イ 行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則と
して、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立
てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行
訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者
や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。
ウ 行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件
について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めて
いるのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束す
る。」と定めている。
エ 行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を
置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査
庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。
オ 行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求め
る訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止
めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない。
1 ア・イ
2 ア・オ
3 イ・エ
4 ウ・エ
5 ウ・オ
14
問題17 処分取消訴訟における訴えの利益の消滅に関する次の記述のうち、最高裁判所の
判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 公務員に対する免職処分の取消訴訟における訴えの利益は、免職処分を受けた公
務員が公職の選挙に立候補した後は、給料請求権等の回復可能性があるか否かにか
かわらず、消滅する。
2 保安林指定解除処分の取消訴訟における訴えの利益は、原告適格の基礎とされた
個別具体的な利益侵害状況が代替施設の設置によって解消するに至った場合には、
消滅する。
3 公文書非公開決定処分の取消訴訟における訴えの利益は、公開請求の対象である
公文書が当該取消訴訟において書証として提出された場合には、消滅する。
4 運転免許停止処分の取消訴訟における訴えの利益は、免許停止期間が経過した場
合であっても、取消判決により原告の名誉・感情・信用等の回復可能性がある場合
には、消滅しない。
5 市立保育所廃止条例を制定する行為の取消訴訟における訴えの利益は、当該保育
所で保育を受けていた原告ら児童の保育の実施期間が満了した場合であっても、当
該条例が廃止されない限り、消滅しない。
15
問題18 抗告訴訟における判決について説明する次のア~オの記述のうち、誤っているも
のの組合せはどれか。
ア 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法であ
ることを宣言することができる。
イ 申請を拒否した処分が判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁
は、速やかに申請を認める処分をしなければならない。
ウ 処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰
することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響
を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを
理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをするこ
とができる。
エ 直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、か
つ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、
裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。
オ 処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行政庁
を拘束すると規定されているが、この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用さ
れない。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ
16
問題19 行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)が定める民衆訴訟および機関訴訟に
関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使
に関する紛争についての訴訟であり、そのような紛争の一方の当事者たる機関は、
特に個別の法律の定めがなくとも、機関たる資格に基づいて訴えを提起することが
できる。
2 民衆訴訟とは、特に法律が定める場合に国または公共団体の機関の法規に適合し
ない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律上の利益にかかわらない資格で何人も
提起することができるものをいう。
3 機関訴訟で、処分の取消しを求めるものについては、行訴法所定の規定を除き、
取消訴訟に関する規定が準用される。
4 公職選挙法が定める地方公共団体の議会の議員の選挙の効力に関する訴訟は、地
方公共団体の機関たる議会の構成に関する訴訟であるから、機関訴訟の一例であ
る。
5 行訴法においては、行政事件訴訟に関し、同法に定めがない事項については、
「民事訴訟の例による」との規定がなされているが、当該規定には、民衆訴訟およ
び機関訴訟を除くとする限定が付されている。
17
問題20 国家賠償に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、その正
誤を正しく示す組合せはどれか。
ア 教科用図書の検定にあたり文部大臣(当時)が指摘する検定意見は、すべて、検
定の合否に直接の影響を及ぼすものではなく、文部大臣の助言、指導の性質を有す
るものにすぎないから、これを付することは、教科書の執筆者または出版社がその
意に反してこれに服さざるを得なくなるなどの特段の事情のない限り、原則とし
て、国家賠償法上違法とならない。
イ 政府が物価の安定等の政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置について
の判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため当該政策目標を達成できな
かった場合、法律上の義務違反ないし違法行為として、国家賠償法上の損害賠償責
任の問題が生ずる。
ウ 町立中学校の生徒が、放課後に課外のクラブ活動中の運動部員から顔面を殴打さ
れたことにより失明した場合において、当該事故の発生する危険性を具体的に予見
することが可能であるような特段の事情のない限り、顧問の教諭が当該クラブ活動
に立ち会っていなかったとしても、当該事故の発生につき当該教諭に過失があると
はいえない。
エ 市内の河川について市が法律上の管理権をもたない場合でも、当該市が地域住民
の要望にこたえて都市排水路の機能の維持及び都市水害の防止など地方公共の目的
を達成するために河川の改修工事をして、これを事実上管理することになったとき
は、当該市は、当該河川の管理につき、国家賠償法 2 条 1 項の責任を負う公共団体
に当たる。
ア イ ウ エ
1 誤 誤 正 正
2 誤 誤 正 誤
3 誤 正 誤 誤
4 正 正 誤 誤
5 正 正 正 誤
18
問題21 国家賠償法 1 条に基づく責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照ら
し、妥当なものはどれか。
1 指定確認検査機関による建築確認に係る建築物について、確認をする権限を有す
る建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関が行った当該確認につい
て、国家賠償法 1 条 1 項の国または公共団体としての責任を負うことはない。
2 公権力の行使に当たる国または公共団体の公務員が、その職務を行うについて、
過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国または公共団体がその被害者
に対して賠償責任を負うが、故意または重過失の場合には、公務員個人が被害者に
対して直接に賠償責任を負う。
3 国または公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うにつ
いて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体が
これを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家
賠償法 1 条 2 項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。
4 国家賠償法1条1 項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件
につき、公務員が主観的に権限行使の意思をもってするものではなく、専ら自己の
利をはかる意図をもってするような場合には、たとえ客観的に職務執行の外形をそ
なえる行為をした場合であったとしても、この要件には該当しない。
5 都道府県警察の警察官が、交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって
違法に他人に損害を加えた場合において、国家賠償法 1 条 1 項により当該損害につ
き賠償責任を負うのは国であり、当該都道府県が賠償責任を負うことはない。
19
問題22 普通地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、
妥当なものはどれか。
1 普通地方公共団体が処理する事務には、地域における事務と、その他の事務で法
律またはこれに基づく政令により処理することとされるものとがある。
2 都道府県の法定受託事務とは、国においてその適正な処理を特に確保する必要が
あるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものであり、都道府県知
事が国の機関として処理することとされている。
3 市町村の法定受託事務とは、国または都道府県においてその適正な処理を特に確
保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものである
から、これにつき市町村が条例を定めることはできない。
4 法定受託事務は、普通地方公共団体が当該団体自身の事務として処理するもので
あるから、地方自治法上の自治事務に含まれる。
5 地方自治法は、かつての同法が定めていた機関委任事務制度のような仕組みを定
めていないため、現行法の下で普通地方公共団体が処理する事務は、その全てが自
治事務である。
問題23 住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照ら
し、妥当でないものはどれか。
1 住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の監査委員に
対して行う。
2 住民訴訟は、あらかじめ、地方自治法に基づく住民監査請求をしていなければ、
適法に提起することができない。
3 住民訴訟で争うことができる事項は、住民監査請求の対象となるものに限定され
る。
4 住民訴訟において原告住民がすることができる請求は、地方自治法が列挙するも
のに限定される。
5 損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴
訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対
して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。
20
問題24 普通地方公共団体の条例または規則に関する次の記述のうち、地方自治法の定め
に照らし、妥当なものはどれか。
1 普通地方公共団体の長が規則を定めるのは、法律または条例による個別の委任が
ある場合に限られる。
2 普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を定めることができる
が、条例において罰則を定めるためには、その旨を委任する個別の法令の定めが必
要である。
3 普通地方公共団体は、特定の者のためにする事務につき手数料を徴収することが
できるが、この手数料については、法律またはこれに基づく政令に定めるものを除
いて、長の定める規則によらなければならない。
4 普通地方公共団体の委員会は、個別の法律の定めるところにより、法令等に違反
しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を定めることができる。
5 普通地方公共団体は条例で罰則を設けることができるが、その内容は禁錮、罰
金、科料などの行政刑罰に限られ、行政上の秩序罰である過料については、長が定
める規則によらなければならない。
21
問題25 公立学校をめぐる裁判に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照
らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア 公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行った場
合、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って
当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比
較してその適否、軽重等を論ずべきである。
イ 教育委員会が、公立学校の教頭で勧奨退職に応じた者を校長に任命した上で同日
退職を承認する処分をした場合において、当該処分が著しく合理性を欠きそのため
これに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといえないと
きは、校長としての退職手当の支出決定は財務会計法規上の義務に違反する違法な
ものには当たらない。
ウ 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、当該施設の
管理者の裁量に委ねられており、学校教育上支障がない場合であっても、学校施設
の目的及び用途と当該使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断に
より許可をしないこともできる。
エ 公立高等学校等の教職員に対し、卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に
向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令がなされた場合におい
て、当該職務命令への違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて、
仮に懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険があるとしても、訴えの要件
である「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。
オ 市立学校教諭が同一市内の他の中学校教諭に転任させる処分を受けた場合におい
て、当該処分が客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴う
ものであるとしても、当該教諭には転任処分の取消しを求める訴えの利益が認めら
れる余地はない。
1 ア・イ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 ウ・エ
5 エ・オ
22
問題26 公文書管理法*について説明する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 公文書管理法に定める「行政文書」とは、同法の定める例外を除き、行政機関の
職員が職務上作成しまたは取得した文書で、当該行政機関の職員が組織的に用いる
ものとして当該行政機関が保有しているものであるとされる。
2 公文書管理法は、行政機関の職員に対し、処理に係る事案が軽微なものである場
合を除き文書を作成しなければならないという文書作成義務を定め、違反した職員
に対する罰則を定めている。
3 行政機関の職員が行政文書を作成・取得したときには、当該行政機関の長は、政
令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、
保存期間および保存期間の満了する日を設定しなければならない。
4 行政機関の長は、行政文書の管理が公文書管理法の規定に基づき適正に行われる
ことを確保するため、行政文書の管理に関する定め(行政文書管理規則)を設けな
ければならない。
5 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の
状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
(注) * 公文書等の管理に関する法律
23
問題27 失踪の宣告に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なも
のはどれか。
1 不在者の生死が 7 年間明らかでない場合において、利害関係人の請求により家庭
裁判所が失踪の宣告をしたときは、失踪の宣告を受けた者は、 7 年間の期間が満了
した時に、死亡したものとみなされる。
2 失踪の宣告を受けた者が実際には生存しており、不法行為により身体的被害を受
けていたとしても、失踪の宣告が取り消されなければ、損害賠償請求権は発生しな
い。
3 失踪の宣告の取消しは、必ず本人の請求によらなければならない。
4 失踪の宣告によって失踪者の財産を得た者は、失踪の宣告が取り消されたとき
は、その受けた利益の全部を返還しなければならない。
5 失踪の宣告によって失踪者の所有する甲土地を相続した者が、甲土地を第三者に
売却した後に、失踪者の生存が判明し、この者の失踪の宣告が取り消された。この
場合において、相続人が失踪者の生存について善意であったときは、第三者が悪意
であっても、甲土地の売買契約による所有権移転の効果に影響しない。
24
問題28 無効および取消しに関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているも
のはどれか。
1 贈与契約が無効であるにもかかわらず、既に贈与者の履行が完了している場合、
受贈者は受け取った目的物を贈与者に返還しなければならず、それが滅失して返還
できないときは、贈与契約が無効であることを知らなかったとしても、その目的物
の現存利益の返還では足りない。
2 売買契約が無効であるにもかかわらず、既に当事者双方の債務の履行が完了して
いる場合、売主は受け取った金銭を善意で費消していたとしても、その全額を返還
しなければならない。
3 秘密証書遺言は、法が定める方式に欠けるものであるときは無効であるが、それ
が自筆証書による遺言の方式を具備しているときは、自筆証書遺言としてその効力
を有する。
4 未成年者が親権者の同意を得ずに締結した契約について、未成年者本人が、制限
行為能力を理由としてこれを取り消す場合、親権者の同意を得る必要はない。
5 取り消すことができる契約につき、取消権を有する当事者が、追認をすることが
できる時以後に、異議をとどめずにその履行を請求した場合、これにより同人は取
消権を失う。
25
問題29 甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよび
Cについて相続が開始した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および
判例に照らし、妥当でないものはどれか。
1 遺産分割が終了していないにもかかわらず、甲につきBが虚偽の登記申請に基づ
いて単独所有名義で相続登記手続を行った上で、これをDに売却して所有権移転登
記手続が行われた場合、Cは、Dに対して、Cの法定相続分に基づく持分権を登記
なくして主張することができる。
2 遺産分割により甲をCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をし
ないうちに、Bが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続
を行った上で、これをEに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、E
に対して、Eの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。
3 Aが甲をCに遺贈していたが、Cが所有権移転登記手続をしないうちに、Bが甲
に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これ
をFに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、Fに対して、Fの持分
権が自己に帰属する旨を主張することができない。
4 Bが相続を放棄したため、甲はCが単独で相続することとなったが、Cが相続登
記手続をしないうちに、Bの債権者であるGが甲に関するBの法定相続分に基づく
持分権につき差押えを申し立てた場合、Cは、当該差押えの無効を主張することが
できない。
5 Aが「甲をCに相続させる」旨の特定財産承継遺言を行っていたが、Cが相続登
記手続をしないうちに、Bが甲に関するBの法定相続分に基づく持分権につき相続
登記手続を行った上で、これをHに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、
民法の規定によれば、Cは、Hに対して、Hの持分権が自己に帰属する旨を主張す
ることができない。
26
問題30 Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのために抵当権が設定さ
れて抵当権設定登記が行われた後、Cのために賃借権が設定され、Cは使用収益を
開始した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥
当なものはどれか。
1 Bの抵当権設定登記後に設定されたCの賃借権はBに対して対抗することができ
ないため、Bは、Cに対して、直ちに抵当権に基づく妨害排除請求として甲の明渡
しを求めることができる。
2 Bの抵当権が実行された場合において、買受人Dは、Cに対して、直ちに所有権
に基づく妨害排除請求として甲の明渡しを求めることができる。
3 AがCに対して有する賃料債権をEに譲渡し、その旨の債権譲渡通知が内容証明
郵便によって行われた後、Bが抵当権に基づく物上代位権の行使として当該賃料債
権に対して差押えを行った場合、当該賃料債権につきCがいまだEに弁済していな
いときは、Cは、Bの賃料支払請求を拒むことができない。
4 Cのための賃借権の設定においてBの抵当権の実行を妨害する目的が認められ、
Cの占有により甲の交換価値の実現が妨げられてBの優先弁済権の行使が困難とな
るような状態がある場合、Aにおいて抵当権に対する侵害が生じないように甲を適
切に維持管理することが期待できるときであっても、Bは、Cに対して、抵当権に
基づく妨害排除請求として甲の直接自己への明渡しを求めることができる。
5 CがAの承諾を得て甲をFに転貸借した場合、Bは、特段の事情がない限り、C
がFに対して有する転貸賃料債権につき、物上代位権を行使することができる。
27
問題31 Aは、Bから金銭を借り受け、Cが、Aの同貸金債務を保証した。次の記述のう
ち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
1 AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名したとき
は、Cが弁済をする資力を有しなくなったときでも、Bは、Aに対し、Cに代えて
資力を有する保証人を立てることを請求することはできない。
2 AがBに対し保証人を立てる義務を負う場合において、BがCを指名するとき
は、Cは、行為能力者でなければならない。
3 BのAに対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、Cに
対しても、その効力を生ずる。
4 Cの保証債務は、Aの債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従
たるすべてのものを包含する。
5 Cは、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することがで
きる。
28
問題32 A所有の動産甲(以下「甲」という。)を、BがCに売却する契約(以下「本件
契約」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当
なものはどれか。
1 Bが、B自身を売主、Cを買主として本件契約を締結した場合であっても、契約
は原則として有効であり、Bは、Aから甲の所有権を取得してCに移転する義務を
負うが、本件契約成立の当初からAには甲を他に譲渡する意思のないことが明確で
あり、甲の所有権をCに移転することができない場合には、本件契約は実現不能な
契約として無効である。
2 Bが、B自身を売主、Cを買主として本件契約を締結した場合であっても、契約
は原則として有効であり、Bは、Aから甲の所有権を取得してCに移転する義務を
負うところ、本件契約後にBが死亡し、AがBを単独相続した場合においては、C
は当然に甲の所有権を取得する。
3 Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主とする本件契約を締結
し、Cに対して甲を現実に引き渡した場合、Cは即時取得により甲の所有権を取得
する。
4 Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主として本件契約を締結
した場合、Bに本件契約の代理権がないことを知らなかったが、そのことについて
過失があるCは、本件契約が無効となった場合であっても、Bに対して履行または
損害賠償の請求をすることができない。
5 Aが法人で、Bがその理事である場合、Aの定款に甲の売却に関しては理事会の
承認が必要である旨の定めがあり、Bが、理事会の承認を得ないままにAを売主、
Cを買主とする本件契約を締結したとき、Cが、その定款の定めを知っていたとし
ても、理事会の承認を得ていると過失なく信じていたときは、本件契約は有効であ
る。
29
問題33 組合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
1 組合の業務の決定は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員
に委任することができるが、第三者に委任することはできない。
2 組合の業務の執行は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員
に委任することができるが、第三者に委任することはできない。
3 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属し、各組合員は、いつ
でも組合財産の分割を請求することができる。
4 組合契約で組合の存続期間を定めた場合であるか、これを定めなかった場合であ
るかを問わず、各組合員は、いつでも脱退することができる。
5 組合契約の定めるところにより一人または数人の組合員に業務の決定および執行
を委任した場合、その組合員は、正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致
によって解任することができる。
問題34 不法行為に基づく損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照
らし、妥当なものはどれか。
1 不法行為による生命侵害の場合において、被害者の相続人であれば、常に近親者
固有の慰謝料請求権が認められる。
2 法人が名誉毀損を受けた場合、法人には感情がないので、財産的損害を除き、非
財産的損害の賠償は認められない。
3 交通事故による被害者が、いわゆる個人会社の唯一の代表取締役であり、被害者
には当該会社の機関としての代替性がなく、被害者と当該会社とが経済的に一体を
なす等の事情の下では、当該会社は、加害者に対し、被害者の負傷のため営業利益
を逸失したことによる賠償を請求することができる。
4 不法行為により身体傷害を受けた被害者は、後遺症が残ったため、労働能力の全
部又は一部の喪失により将来において取得すべき利益を喪失した場合には、その損
害について定期金ではなく、一時金による一括賠償しか求めることができない。
5 交通事故の被害者が後遺症により労働能力の一部を喪失した場合に、その後に被
害者が別原因で死亡したとしても、交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体
的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事
情がない限り、死亡の事実は逸失利益に関する就労可能期間の認定において考慮さ
れない。
30
問題35 共同相続における遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照
らし、妥当なものはどれか。
1 共同相続人中の特定の 1 人に相続財産中の不動産の所有権を取得させる一方で当
該相続人が老親介護を負担する義務を負う内容の遺産分割協議がなされた場合にお
いて、当該相続人が遺産分割協議に定められた介護を行わない場合には、他の共同
相続人は債務不履行を理由として遺産分割協議自体を解除することができる。
2 被相続人が、相続財産中の特定の銀行預金を共同相続人中の特定の 1 人に相続さ
せる旨の遺言をしていた場合、当該預金債権の価額が当該相続人の法定相続分の価
額を超えるときには、当該預金債権の承継に関する債権譲渡の対抗要件を備えなけ
れば、当該預金債権の承継を第三者に対抗できない。
3 共同相続人の 1 人が、相続開始後遺産分割の前に、被相続人が自宅に保管してい
た現金を自己のために費消した場合であっても、遺産分割の対象となる財産は、遺
産分割時に現存する相続財産のみである。
4 共同相続人は、原則としていつでも協議によって遺産の全部または一部の分割を
することができ、協議が調わないときは、家庭裁判所に調停または審判の申立てを
することができるが、相続開始から 10 年以上放置されていた遺産の分割について
は、家庭裁判所に対して調停または審判の申立てを行うことができない。
5 相続財産中に銀行預金が含まれる場合、当該預金は遺産分割の対象となるから、
相続開始後遺産分割の前に、当該預金口座から預金の一部を引き出すためには共同
相続人の全員の同意が必要であり、目的、金額のいかんを問わず相続人の 1 人が単
独で行うことは許されない。
31
問題36 匿名組合における匿名組合員に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、
誤っているものはどれか。
1 匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
2 匿名組合員は、匿名組合契約に基づき営業者が負った債務について、当該匿名組
合員が匿名組合の当事者であることをその債務に係る債権者が知っていたときに
は、当該営業者と連帯して弁済する責任を負う。
3 出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名
組合員は、利益の配当を請求することができない。
4 匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、営業者の業
務及び財産の状況を検査することができる。
5 匿名組合員が破産手続開始の決定を受けた場合、匿名組合契約は終了する。
問題37 株主の議決権に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しい
ものの組合せはどれか。
ア 株主総会における議決権の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を生じな
い。
イ 株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
ウ 取締役候補者である株主は、自らの取締役選任決議について特別の利害関係を有
する者として議決に加わることができない。
エ 監査役を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができ
る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半
数をもって行う。
オ 役員等がその任務を怠ったために株式会社に生じた損害を賠償する責任を負うこ
ととなった場合に、当該責任を免除するには、議決権のない株主を含めた総株主の
同意がなければならない。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ
32
問題38 監査等委員会設置会社の取締役の報酬等に関する次の記述のうち、会社法の規定
に照らし、誤っているものはどれか。
1 取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役と
を区別して定めなければならない。
2 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬
等について意見を述べることができる。
3 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取
締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
4 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がな
いときは、当該報酬等は、株主総会で決議された取締役の報酬等の範囲内におい
て、監査等委員である取締役の多数決によって定める。
5 監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総
会の決議により定められている場合を除き、当該取締役の個人別の報酬等の内容に
ついての決定に関する方針を取締役会で決定しなければならない。
問題39 株式交換に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれ
か。
1 株式交換完全親会社は、株式会社でなければならない。
2 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の発行済株式の一部のみを取得する
こととなる株式交換を行うことができる。
3 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に対し、当該株式交換完全親
会社の株式に代わる金銭等を交付することができる。
4 株式交換完全親会社の反対株主は、当該株式交換完全親会社に対し、自己の有す
る株式を公正な価格で買い取ることを請求することはできない。
5 株式交換契約新株予約権が付された、株式交換完全子会社の新株予約権付社債の
社債権者は、当該株式交換完全子会社に対し、株式交換について異議を述べること
はできない。
33
問題40 会社訴訟に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはど
れか。なお、定款に別段の定めがないものとする。
1 株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、当該株主総会決議の日から 3 か
月以内に、訴えをもってのみ当該決議の取消しを請求することができる。
2 会社の設立無効は、会社の成立の日から 2 年以内に、訴えをもってのみ主張でき
る。
3 新株発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決にお
いて無効とされた行為は、将来に向かってその効力を失う。
4 6 か月前から引き続き株式を有する株主は、公開会社に対し、役員等の責任を追
及する訴えの提起を請求することができる。
5 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社及び当該解任を請求された役員を
被告とする。
34
[問題41~問題43は択一式(多肢選択式)]
問題41 次の文章は、婚外子の法定相続分を嫡出である子の 2 分の 1 と定めていた民法規
定(以下「本件規定」という。)を違憲とした最高裁判所の決定の一部である。空
欄 ア ~ エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 ~20)から選びなさい。
本件規定は、国民生活や身分関係の基本法である民法の一部を構成し、相続という
日常的な現象を規律する規定であって、〔問題となった相続が開始した〕平成 13年7
月から既に約 12 年もの期間が経過していることからすると、その間に、本件規定の
合憲性を前提として、多くの遺産の分割が行われ、更にそれを基に新たな権利関係が
形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け、本決定の
違憲判断は、長期にわたる社会状況の変化に照らし、本件規定がその合理性を失った
ことを理由として、その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするものである。そ
れにもかかわらず、本決定の違憲判断が、 ア としての イ という形で既に行われ
た遺産の分割等の効力にも影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすること
は、著しく ウ を害することになる。 ウ は法に内在する普遍的な要請であり、当
裁判所の違憲判断も、その ア としての イ を限定し、 ウ の確保との調和を図
ることが求められているといわなければならず、このことは、裁判において本件規定
を違憲と判断することの適否という点からも問題となり得るところといえる。
以上の観点からすると、既に関係者間において裁判、合意等により エ なものと
なったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法
律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされ
た本件規定の適用を排除した上で法律関係を エ なものとするのが相当であるとい
える。
(最大決平成 25 年 9 月 4 日民集 67 巻 6 号 1320 頁<文章を一部変更した。>)
1 公権力 2 事実上の拘束性 3 影響力の行使 4 法的安定性
5 衡平 6 暫定的 7 対話 8 先例
9 法令審査 10 確定的 11 具体的 12 家族法秩序
13 終審裁判所 14 既判力 15 司法積極主義 16 遡及的
17 実質的正義 18 蓋然的 19 公益 20 裁量統制
35
問題42 次の文章の空欄 ア ~ エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 ~20)から
選びなさい。
特定の公益事業の用に供するために、私人の特定の財産権を強制的に取得し、また
は消滅させることを、 ア といい、これについて定めた代表的な法律として土地収
用法が存在する。
土地収用法は、土地収用の手続および補償について定めるが、補償の要否および範
囲をめぐって訴訟が提起されることがある。同法 88 条は、他の条文で規定する損失
に加えて、その他土地を収用し、または使用することによって発生する土地所有者ま
たは関係人の「 イ 損失」を補償する旨定めているが、この規定をめぐって、いわ
ゆる輪中堤の文化財的価値が損失補償の対象となるか否かが争われた事案がある。
昭和 63 年 1 月 21 日の最高裁判決は、同条にいう「 イ 損失」とは、客観的社会
的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・ ウ
な損失をいうと解するのが相当であって、経済的価値でない特殊な価値については補
償の対象とならないとした。そして、由緒ある書画、刀剣、工芸品等のように、その
美術性・歴史性などのいわゆる文化財的価値なるものが、当該物件の取引価格に反映
し、その エ を形成する一要素となる場合には、かかる文化財的価値を反映した
エ がその物件の補償されるべき相当な価格となるが、他方で、貝塚、古戦場、関
跡などにみられるような、主としてそれによって国の歴史を理解し往時の生活・文化
等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該
土地の不動産としての経済的・ ウ 価値を何ら高めるものではなく、その エ の形
成に影響を与えることはないから、このような意味での文化財的価値は、それ自体経
済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ないと判
示し、輪中堤の文化財的価値に対する損失補償を否定した。
1 強制徴収 2 特殊利益 3 受忍限度内の
4 財産的 5 適正な 6 社会通念
7 特別の犠牲 8 都市計画 9 合理的
10 市場価格 11 法律により保護された 12 絶対的
13 公用収用 14 所有権 15 反射的
16 権利利益 17 国家補償 18 通常受ける
19 精神的 20 行政上の強制執行
36
問題43 次の文章の空欄 ア ~ エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 ~20)から
選びなさい。
参議院の総議員の 4 分の 1 以上である 72 名の議員は、平成 29 年 6 月 22 日、憲法
53 条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定すること(以下
「臨時会召集決定」という。)を要求した。内閣は、同年 9 月 22 日、臨時会を同月
28 日に召集することを決定した。同日、第 194 回国会が召集されたが、その冒頭で
衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。本件は、上記の要求をした参議院
議員の一人である上告人(原告)が、被上告人(国)に対し、主位的に、上告人が次
に参議院の総議員の 4 分の 1 以上の議員の一人として臨時会召集決定の要求(以下
「臨時会召集要求」という。)をした場合に、内閣において、20 日以内に臨時会が召
集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合
に、上告人が 20 日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求め
る(以下、これらの請求に係る訴えを「本件各確認の訴え」という。)事案である。
本件各確認の訴えは、上告人が、個々の国会議員が臨時会召集要求に係る権利を有
するという憲法 53 条後段の解釈を前提に、 ア に関する確認の訴えとして、上告人
を含む参議院議員が同条後段の規定により上記権利を行使した場合に被上告人が上告
人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を
求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否
に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであ
るということができる。そうすると、本件各確認の訴えは、 イ に当たるというべ
きであり、これと異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわ
ざるを得ない。
もっとも、本件各確認の訴えは、将来、上告人を含む参議院議員が憲法 53 条後段
の規定により臨時会召集要求をした場合における臨時会召集決定の遅滞によって上告
人自身に生ずる不利益を防止することを目的とする訴えであると解されるところ、将
来、上告人を含む参議院の総議員の 4 分の 1 以上により臨時会召集要求がされるか否
かや、それがされた場合に臨時会召集決定がいつされるかは現時点では明らかでない
といわざるを得ない。
そうすると、上告人に上記不利益が生ずる ウ があるとはいえず、本件各確認の
訴えは、 エ を欠き、不適法であるというべきであるから、これを却下すべきもの
とした原審の判断は、結論において是認することができる。
(最三小判令和 5 年 9 月 12 日民集 77 巻 6 号 1515 頁<文章を一部修正した。>)
37
1 法律上保護された利益
3 確認の利益
5 合理的な理由
7 法律上の争訟
9 処分たる性格
11 制度上の障害
13 現実の危険
15 被告適格
17 機関相互間における権限の存否又は
その行使
19 自己の法律上の利益にかかわる資格
で提起する訴訟
2 予見可能性
4 統治行為
6 公権力の行使に関する不服の訴訟
8 国権の発動
10 相当の蓋然性
12 国会議員の資格
14 確認の対象
16 公法上の法律関係
18 当事者間の法律関係を確認し又は形
成する処分又は裁決に関する訴訟
20 国又は公共団体の機関の法規に適合
しない行為の是正を求める訴訟
38
問題44 総務大臣Yは、新たなテレビ放送局の開設を目的として、電波法に基づく無線局
開設免許を 1 社のみに付与することを表明した。これを受けて、テレビ放送局を開
設しようとする会社XがYに開設免許の申請をしたところ、Yは、その他の競願者
の申請を含めて審査を実施し、会社Aに対しては免許を付与する処分(免許処分)
をし、Xに対しては申請を棄却する処分(拒否処分)をした。
これに対し、Xは取消訴訟を提起して裁判上の救済を求めたいと考えている。競
願関係をめぐる最高裁判所の判例の考え方に照らし、Xは誰を被告として、どのよ
うな処分に対する取消訴訟を提起できるか。なお、現行の電波法は、審査請求前置
や裁決主義の規定を置いているが、それらは度外視して、直接に処分取消訴訟がで
きるものとして考え、40 字程度で記述しなさい。
(下書用)
問題45 Aは、海外からコーヒー豆を輸入して国内の卸売業者に販売する事業を営んでい
る。Aは、卸売業者Bにコーヒー豆 1 トン(以下「甲」という。)を販売し、甲
は、B所有の倉庫内に第三者に転売されることなくそのまま保管されている。A
は、Bに対し、甲の売買代金について、その支払期限経過後、支払って欲しい旨を
伝えたが、Bは、経営不振を理由に、いまだAに支払っていない。BにはA以外に
も一般債権者がいる。この場合に、Aは、甲についていかなる権利に基づき、どの
ような形で売買代金を確保することができるか。民法の規定に照らし、40 字程度
で記述しなさい。
(下書用)
10 15
10 15
[問題44~問題46は記述式] 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄(マス目)に記述す ( ) ること。なお、字数には、句読点も含む。
39
問題46 Aは、Bとの間で、BがCから購入した甲土地(以下「甲」という。)を買い受
ける契約を締結し、Bに対して代金全額を支払ったが、甲の登記名義はいまだCの
ままである。BC間の売買において、CがBへの移転登記を拒む理由は存在せず、
また、BがCに対して移転登記手続をすべきことを請求している事実もない。一
方、Aは、早期に甲の所有権取得の対抗要件として登記を具備したい。
このような場合、Aは、何のために、誰の誰に対するいかなる権利を、どのよう
に行使できるか。40 字程度で記述しなさい。
(下書用) 10 15
40
基礎知識 [問題47~問題60は択一式( 5 肢択一式)]
問題47 政治に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1 政党助成法は、衆議院または参議院に一定数以上の議席を有するか、議席を有し
て一定の国政選挙で有効投票総数の一定割合以上の得票があった政党に対して、政
党交付金による助成を行う旨を規定している。
2 マス・メディアなどの情報に対して、主体的に世論を形成するためなどに、それ
らを批判的に読み解く能力は、メディア・リテラシーと呼ばれる。
3 政治資金規正法は、政治資金の収支の公開や寄附の規制などを通じ政治活動の公
明と公正を確保するためのルールを規定している。
4 有権者のうち、特定の支持政党を持たない層は、無党派層と呼ばれる。
5 性差に起因して起こる女性に対する差別や不平等に反対し、それらの権利を男性
と同等にして女性の能力や役割の発展を目指す主張や運動は、ポピュリズムと呼ば
れる。
問題48 中東やパレスチナに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1 1947 年に、国際連合総会において、パレスチナをアラブ人国家とユダヤ人国家
と国際管理地区とに分割する決議が採択された。
2 1948 年に、イスラエルの建国が宣言されると、これに反発したアラブ諸国との
間で第一次中東戦争が勃発した。
3 1987 年に、イスラエルの占領地で始まり、大規模な民衆蜂起に発展したパレス
チナ人による抵抗運動を、第一次インティファーダ(民衆蜂起)という。
4 1993 年に、パレスチナ解放機構(PLO)とイスラエルとの間で暫定自治協定が
結ばれ、(ヨルダン川)西岸地区・ガザ地区でパレスチナの先行自治が始まった。
5 2020 年に、日本が仲介して、イスラエルとアラブ首長国連邦(UAE)およびイ
ランが、国交の正常化に合意した。
41
問題49 日本円の外国為替に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 1931 年に金輸出が解禁されて金本位制に基づく日米英間の金融自由化が進み、
ソ連・中国・ドイツの統制経済圏を包囲する自由経済圏が成立した。
2 1949 年に 1 ドル= 360 円の単一為替レートが設定されたが、ニクソンショック
を受けて、1971 年には 1 ドル= 308 円に変更された。
3 1973 年には固定相場制が廃止され、変動相場制に移行したため、その後の為替
レートは、IMF(国際通貨基金)理事会で決定されている。
4 1985 年のいわゆるレイキャビック合意により、合意直前の 1 ドル= 240 円か
ら、数年後には 1 ドル= 120 円へと、円安ドル高が起きた。
5 2014 年には、「戦後レジーム(ワシントン・コンセンサス)を取り戻す」ことを
目指した通称「アベノミクス」により、 1 ドル= 360 円になった。
問題50 日本における外国人に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはど
れか。
ア 外国籍の生徒も、全国高等学校体育連盟や日本高等学校野球連盟が主催する大会
に参加することができる。
イ より広い業種での外国人の就労を可能とするために新たに設けられた在留資格
「特定技能 1 号」には、医師も含まれる。
ウ 徴税など、いわゆる公権力の行使にあたる業務を含め、外国籍の者も全国の全て
の自治体で公務員として就労することができる。
エ 名古屋出入国在留管理局の施設に収容されていたスリランカ人女性が 2021 年に
死亡し、その遺族が国家賠償請求訴訟を行った。
オ 特別永住者を含む外国人には、日本への入国時に指紋と顔写真の情報の提供が義
務付けられている。
1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 ウ・オ
5 エ・オ
42
問題51 ジェンダーに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 世界経済フォーラムが毎年発表しているジェンダーギャップ指数において、2006
年の開始以来、日本は常に上位 10 位以内に入っている。
2 出生時に割り当てられた性別に対し苦痛を感じている人が受けるホルモン療法や
性別適合手術等の医療技術のことを、フェムテックという。
3 レインボーフラッグは、性の多様性を尊重するシンボルとして用いられている。
4 複数の大学の医学部の入学試験で、性別を理由に男性の受験生が不当に減点され
ていたことが 2018 年に明らかになり、訴訟となった例もある。
5 働く女性が妊娠・出産を理由に解雇・雇止めをされることや、妊娠・出産にあ
たって職場で受ける精神的・肉体的なハラスメントを、カスタマー・ハラスメント
という。
問題52 行政書士法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲
示しなければならない。
2 行政書士は、自ら作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請
求について、その手続を代理することはできない。
3 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して 2 年以
上になる者は、行政書士となる資格を有する。
4 破産手続開始の決定を受けた場合、復権をした後においても行政書士となる資格
を有しない。
5 地方公務員が懲戒免職の処分を受けた場合、無期限に行政書士となる資格を有し
ない。
43
問題53 住民基本台帳法に明示されている住民票の記載事項に関する次の項目のうち、妥
当なものはどれか。
1 前年度の住民税納税額
2 緊急時に連絡可能な者の連絡先
3 地震保険の被保険者である者については、その資格に関する事項
4 海外渡航歴
5 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主と
の続柄
問題54 デジタル環境での情報流通に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1 生成 AI が、利用者からの質問を受けて、誤った情報をあたかも真実であるかの
ように回答する現象を、アノテーションという。
2 情報が大量に流通する環境の中で、人々が費やせるアテンションや消費時間が希
少になり、それらが経済的価値を持つようになることを、アテンションエコノミー
という。
3 SNS などを運営する事業者が、違法コンテンツや利用規約違反コンテンツを削
除することなどを、コンテンツモデレーションという。
4 SNS などで流通する情報について、第三者がその真偽を検証して結果を公表す
るなどの活動を、ファクトチェックという。
5 SNS などのアルゴリズムにより、自分の興味のある情報だけに囲まれてしまう
状況を、フィルターバブルという。
44
問題55 欧米の情報通信法制に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1 EU のデジタルサービス法(DSA)は、SNS などのプラットフォーム事業者に対
して、事業者の規模などに応じた利用者保護などのための義務を課している。
2 EU のデジタル市場法(DMA)は、SNS などのプラットフォーム事業者に対し
て、著作権侵害コンテンツへの対策を義務付けている。
3 EU の一般データ保護規則(GDPR)では、個人データによるプロファイリング
に異議を唱える権利や、データポータビリティの権利が個人に付与されている。
4 米国では、児童オンラインプライバシー保護など分野ごとに様々な個人情報保護
関連の連邦法が存在する。
5 米国では、包括的な個人情報保護を定めた州法が存在する州がある。
問題56 デジタル庁に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 デジタル庁は、総務省に置かれている。
2 デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。
3 デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦
略本部が置かれている。
4 デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っ
ている。
5 デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は
含まれていない。
45
問題57 個人情報保護法*に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1 個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害す
るおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告を行わなければならな
い。
2 個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれ
がある方法により個人情報を利用してはならない。
3 個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供をした場合には、原則として、
当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報
保護委員会規則で定める事項を記録しなければならない。
4 学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業
者の義務に関する規定は適用されない。
5 国の行政機関や地方公共団体の機関にも、個人情報保護法の規定は適用される。
(注) * 個人情報の保護に関する法律